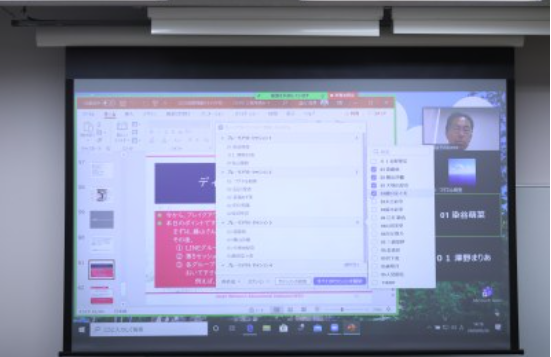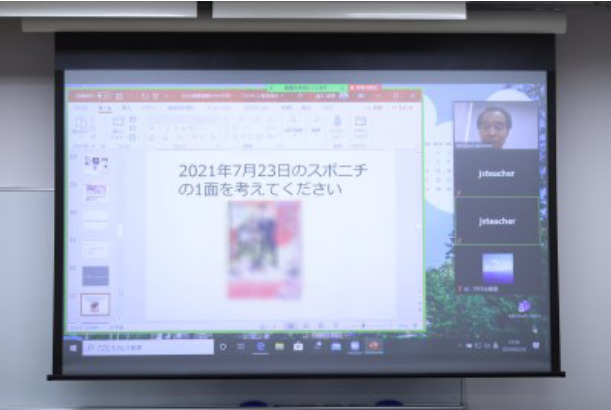社会や環境を意識した消費行動として注目される「エシカル消費」の理解を深める授業が11月26日(火)、一般社団法人エシカル協会代表理事の末吉里花氏を講師に招いて、本学日野キャンパスで行われました。生活科学部生活環境学科の大川知子准教授が担当する「消費科学」(後期2単位)の一環で、同科目を選択した4年生25人が聴講。国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の実践の一つとして期待されているエシカル消費の意義や仕組みを学びました。
演題は「私たちの選択が未来を変える~エシカル消費のすすめ~」。末吉講師は、TBS系列の「日立 世界ふしぎ発見!」の元ミステリーハンター(レポーター)で、“秘境班”メンバーとして世界中を旅しました。その旅の一つで登ったのが、アフリカ・キリマンジャロ山でした。その際、目の当たりにした地球温暖化による山頂の氷河の融解。これが、末吉講師が環境問題に目覚めるきっかけとなり、やがてフェアトレードと邂逅。そして2015年のエシカル協会を立ち上げにつながり、今日の活動に至るパーソナル・ストーリーを語りました。
エシカル消費でSDGs実現へ
では、そもそもエシカル消費とは何でしょう。一般的に「地域の活性化、雇用なども含む、人や社会、地球環境に配慮した消費やサービスのこと」を指すといわれていますが、末吉講師は、エシカル消費はさらに多面的であり、「モノの過去、現在、未来を考えて消費をすること」「ストーリー、物語があること」「モノの背景が分かること」と指摘しています。
末吉講師は聴講する学生に語り掛けます。「皆さんはもう、SDGs(持続可能な開発目標)を学びましたか」。SDGsは全世界の人々が2030年までに達成すべき目標として17個の目標を掲げていますが、このうち12番目の「つくる責任つかう責任」の達成に「エシカル消費はものすごくいい、有効な手段である」と強調しています。
実際、企業に限らず政府(消費者庁や環境省など)や地方自治体(長野県や徳島県など)でもエシカル消費の普及を目指す動きが始まっており、2021年からの中学校、2022年からの高校の新学習指導要領に基づく教科書にはエシカル消費の話題が登場します。「5年後にはガラリと違う世の中になっている」という末吉講師が願う未来は、あながち過大な期待とはいえなくなっています。
ところで、そもそもエシカル消費はなぜ必要とされるのでしょうか。末吉講師は「消費者が求める製品の安さの背景には、弱い立場にある途上国の生産者の犠牲があるかもしれないからだ」と語ります。
背景に途上国の劣悪な労働環境
グローバル化が進んだ今日、毎日消費する製品を誰が、どこで、どうやって、どのように作っているのか、ほとんど分かりません。洋服の原料のコットン、チョコレートの原料のカカオ、そしてサッカーボール…。多くは途上国で作られていますが、その生産背景に労働搾取や児童労働、環境破壊といった深刻な問題が潜んでいたとしても、製品から背後の見えない問題は分かりません。このため、私たちは知らない間に、日常の消費を通じて、こうした人権侵害や環境破壊に加担しているかもしれないと末吉講師は言います。
2013年4月、バングラデシュの首都ダッカ近郊の縫製工場が入った商業ビル「ラナ・プラザ」が崩落し、1,100人以上の工場労働者が犠牲になりました。ファッション史上最悪の汚点と語り継がれていますが、この工場では劣悪な労働環境の中で主に、安いからと先進国の消費者が好んで購入するファストファッションや、世界展開する欧米や日本のアパレルブランドの商品がつくられていました。
社会を変える、企業に声届ける
では私たちに社会の課題解決で何ができるのでしょう。とりわけ、学生には-。末吉講師は「消費者としての力を発揮しながら、一人ひとりが声をあげよう、企業に届けよう。それが社会を変革する最も強力な手段です」と訴えます。
末吉講師によると、自分が出すゴミを一年間ノートに記録し続けた女子大生たちがいた、といいます。プラスチックのゴミがすごく多かったそうです。そして彼女たちは書き出すだけでなく行動を起こし、スーパーや店に声を届けました。「プラスチックのモノはできるだけ買いたくありません。だから代えてください」と訴えました。
大手スーパーのイオンはフェアトレードの商品を販売するリーディングカンパニーともいえる存在ですが、その取り組みはたった一人の主婦の声から始まりました。
また、末吉講師は教室の学生に向け、こう続けました。「皆さん、日々の暮らし、学校生活を通じて社会に変革を起こして下さい。皆さん一人ひとりその力を持っています」。
「ファエトレード大学」という制度があるそうです。英国では170大学以上が認証を受けており、日本では2018年2月の静岡文化芸術大学が国内認定第1号で、2019年10月の札幌学院大学と北星学園大学の同時認定が第2号で続きました。
国際基督教大学(ICU)は同窓会オリジナルグッズにフェアトレード認証コットンを使ったオリジナルグッズとブックカバーをつくり、毎年大人気ですごい売れ行きといいます。
広がり始めたエシカル消費。とはいえ、末吉講師が壁にぶち当たり活動をやめようと思ったことは一度や二度ではなかったといいます。そのたび、自らを奮い立たせたのが、パタゴニア創設者イヴォン・シュイナード氏から贈られた言葉だったそうです。「活動を今やめてしまったら、あなたも問題の一部になる」。末吉講師は授業の締め括りとして「仲間がいると、いろんなことがしやすい。1人の百歩よりも100人の一歩が世界を変える」と語り、90分間の講演を結びました。