共通教育科目「実践プロジェクトc」(担当:生活科学部生活環境学科 一色 ヒロタカ准教授)の授業が4月10日に始まりました。株式会社テレビ東京のテレビ番組『田村淳のTaMaRiBa』からのご協力のもと、日野市の地域課題解決を目指す特別講座です。この日のオリエンテーションではイノベーションを起こす大切さを学び、学生たちは積極的に授業に取り組む姿勢を見せていました。
ひとつの企業ではできないことも連携すれば生み出せる
登壇されたのはテレビ東京のプロデューサーである今井豪氏です。
ふだんゲスト講師の方が来られたときは、講師の方のみで講義をされますが、そこは多くのテレビ番組を製作してきた今井氏。
「台本を作ってきました」と、一色先生にもマイクが渡されました。一色先生が「台本を見てびっくりしたんですけど、僕のセリフもちゃんと書いてあって」と話すと学生たちからも笑い声が。
そのやりとりの通り、今井氏は1回限りのゲストではなく、建築家でもある一色先生とともに前期を通して授業を担当してくださいます。学生たちの提案を形にするためにバックアップしてくれる贅沢な環境です。


今井氏は入社からテレビ東京一筋。
バラエティ番組の企画や開発に携わっていましたが、東日本大震災をきっかけに「なぜテレビ番組を作っているのだろうと考えた」と言います。
テレビの力で復興や地域の役に立ちたいと考えましたが、一つの企業では限界がありました。悔しさを感じていたところ、他の最先端技術を持つ企業の人たちも同じように話していたのを知ります。
そして企業が連携すれば新しいサービスを生み出せることに魅力を感じ、ビジネス共創番組『田村淳のTaMaRiBa』をスタートさせました。
テレビ番組と連携して日野のまちの地域創生しよう!
「地域の困りごとをほったらかしにしない」と2022年から始まった『田村淳のTaMaRiBa』。
島根県江津市のリブランディングや、沖縄の三線の音源をデジタルで残すプロジェクトなどさまざまな地域の課題に取り組んでいます。
また、大学生と一緒にサービスや商品開発などの地域創生につながる活動も行っています。
本授業ではこの番組のプラットフォームをお借りして、本学日野キャンパスがある東京都日野市を舞台に、自治体や企業と連携し課題解決に挑みます。
授業の進め方としては、まずはフィールドワークで街のリサーチから始まります。
日野の街を実際に歩いたりヒアリングしたり、本やウェブも活用して課題や可能性を見つけていきます。
次に企画作り。街の仕組みを変えてみるアイディアや居場所作りなど、さまざまな視点から街を見て、ビジネスプランや課題解決のアイディアを具体的に作っていきます。
発表を経て、実際にデザインに起こします。
そして、最終プレゼンテーションではスタジオでの収録も予定されています。
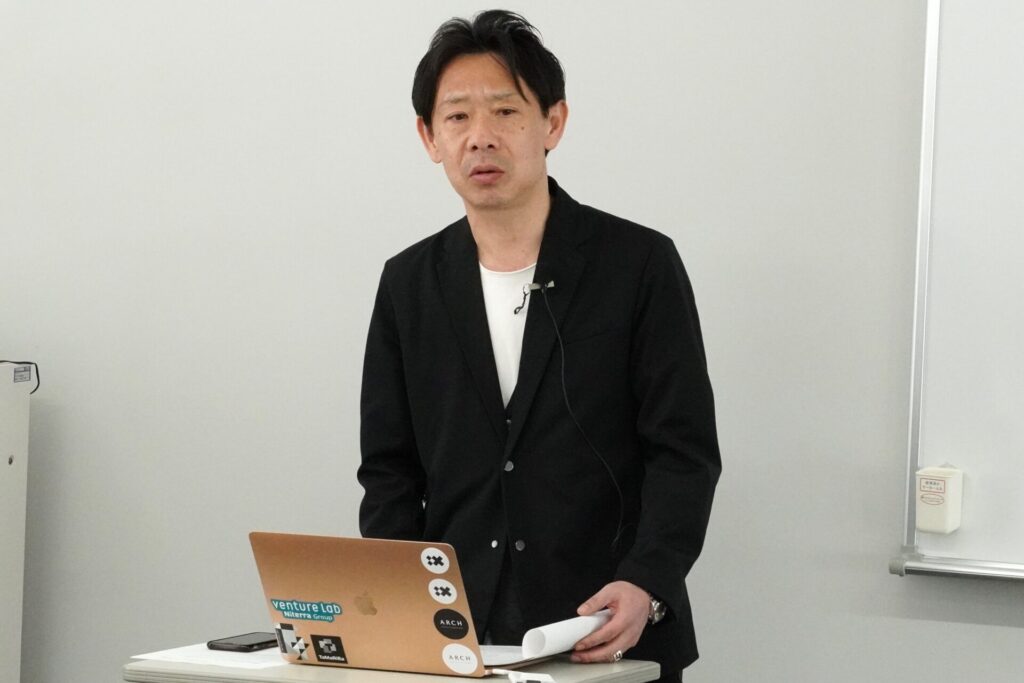
イノベーションは誰にでも起こせる

この授業に取り組むうえで大切にして欲しい合言葉として、今井氏が提示したのが「イノベーションって天才たちの発明なんかじゃない!」でした。
今井氏は「これは身をもって痛感し、信じている言葉です」と話しました。イノベーションは新しいテクノロジーと思われることがありますが、「新結合」の意味で、誰もが知っていることを新たに結びつけること。
自分の持っているものと課題を掛け合わせることで、イノベーションを起こすことができるのです。
イノベーションを起こすためには自分の本当の強みを知り、どうビジネスや社会に活かせるかを考えることが大切。
一色先生は「授業の中で自分をいかにブラッシュアップしていけるかがポイントです」と話しました。
グループワークで進めますが、企業や自治体、街に住む人たちと実際に交流をするのもこの授業の特徴です。
「沢山の人と会って話して、自分がやりたいことや得意なことを見つけたり活かしたりして欲しい」と今井氏も話しました。
まずは日野のまちを知ろう
最後に来週への課題が発表されました。
1つ目は日野がどういうところか、自分なりに調べること。
地形や風景、歴史、特徴、観光地的な魅力、企業などなど。特徴をあぶり出すことが課題です。
2つ目は誰のためにやってみたいか、ターゲットを決めること。
ペルソナと言って仮想の人物像を作り上げていく作業です。フルネームから性別、年齢、休日の過ごし方、仕事など一から考えます。
条件は日野に住んでいる、または日野で働いている人物であること。
そして、インサイトと呼ばれる、その人物の抱いている不満や悩みなども書き出してみることが課題です。
「今回の授業はビジネスの感性を磨いたり自分のやりたいことを見つけたりするのにも、とても向いていると思います」と今井氏は語ります。
「今ビジネスでは、実際にアイディアを形にできるアートの感性が成功するために不可欠な要素になっています」と言い、どうやって自分の形を表現していくかの授業は日本では少ないため、貴重な経験になると話しました。
ただ「この授業はなかなか大変だと思います」と一色先生。「ものやサービスを作ることはそんなに簡単じゃない。とても時間がかかることです。14回の授業だけで全部を作れると思わなくていいので、ここをスタートにして大きな企画になっていくかもしれないという気持ちで取り組んでください」と話しました。
学生たちも、これからの授業の展望に前のめりで話を聞いていました。

担当教員からのメッセージ
地域から学ぶことの面白さ!そして、そこからデザインを考える面白さ!これは社会実装型の授業の最大の醍醐味です。社会のニーズも、答えを自分でつくり出せる人材を求めています。この授業では、まさにリアルな社会から自分自身の答えをつくりだし、その答えを持って社会へアプローチしていきます。学生と教員が協働・共創して、日野のまちをデザインしていいきます。




