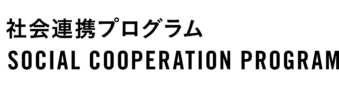東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会からもうすぐ1年となる7月5日(火)、五輪女子マラソンメダリストの有森裕子さんが本学渋谷キャンパスを訪れ、特別講義を行いました。有森さんは、新型コロナウイルス感染症拡大により原則無観客で行われた前例のない大会を振り返り、「五輪は選手だけでなく見る人、支える人、すべての人々が主役の祭典。国と国の対抗戦でもない」と、五輪憲章に立ち返りその意義を見直す必要があると語り、「未来の五輪を変えていけるのは、大会運営当事者ではなく皆さんの声だけ。人ごとと考えずに自分の声で五輪を変えていく楽しみを見いだしてほしい」と呼び掛けました。

「自分で自分をほめたい」、あの名言から26年。東京五輪のレガシーとは


2、3年生が対象のキャリア教育科目「国際理解とキャリア形成」の一環として行われたこの特別講義。2020年、2021年に続き、五輪女子マラソンメダリストの有森裕子さんとスポーツニッポン新聞社の藤山健二編集委員との対談が実現しました。指導教授は文学部国文学科の深澤晶久教授(キャリア教育)です。
冒頭は、1996年のアトランタ五輪の女子マラソンに出場した有森さんが、見事銅メダルを獲得した直後のインタビュー映像を視聴するところからスタートしました。1996年の新語・流行語大賞にも選ばれた「自分で自分をほめたい」というあの名言が生まれたのは、まさにこの時です。あれから26年――、コロナ禍で1年延期、原則無観客という異例の状況下で開催された東京五輪から間もなく1年がたとうとしています。有森さんは大会開催当時を振り返り、「本来、東京五輪が開催されるはずだった2020年からすでに2年以上たっているが、なんともスッキリしない」と話します。「東京五輪の余韻はあっさりしていて、どこか冷めた感がある。オリンピアンの一人として五輪の基本に立ち返らなければいけないと思うようになった」。
一方で、東京五輪での日本人選手の活躍には目覚ましいものがありました。有森さんが2度目のメダルを手にしたアトランタ五輪での日本人のメダル獲得数は、金3個、銀6個、銅5個の計14個。それに対し昨年の東京五輪では、金27個、銀14個、銅17個の計58個と、日本人選手の競技力は確実に向上しています。それでも有森さんは「東京五輪には振り返る内容が乏しい」といいます。「コロナ禍での異例の開催となったことで、大会開催前に想定していたレガシー創出は実現できなかった。これは仕方のない結果だが、今もなお東京五輪のレガシーは何だったのか問い続けている状況にある」。
とはいえ、ソーシャルインクルージョンの実現には東京五輪の開催がプラスに働いたと続けます。「選手だけでなく、観客や運営サイド、さまざまな人たちのことをあらゆる角度から考える機会となったことには意義があった。大会後はパラリンピアンからの発信が増え、彼らを支えるスポンサーも当然のように増えた。障害は決して特別なものではなく、自分たちもいつでも障害者になり得る。すべての人たちが社会に参画する機会を持ち、共に生きていくことについて考える頻度が高まったことは喜ばしい」。
今こそ五輪憲章の基本に立ち返るとき
「五輪の主役は選手だけではない。観客も、運営スタッフも、ボランティアも、すべての人が主役」と話す有森さん。だからこそ、原則無観客での東京五輪は異様な大会だったと指摘します。「選手は参加したという満足度を得られたかもしれないが、観客という大きな主役を欠いての開催は異常だったと言わざるを得ない」。その言葉を受けて「選手の声だけが響く会場の様子を記事にするのには苦労した」と回顧した藤山氏は、ロシアの軍事侵攻が五輪休戦決議違反だと非難されている点に話を移しました。「五輪開幕の7日前からパラリンピック閉幕の7日後までを休戦とする」という五輪休戦決議は193のすべての国連加盟国によって採択されましたが、ロシアは北京五輪閉幕後間もなくウクライナへの侵攻を開始。ロシアおよび同盟国であるベラルーシの選手たちは、北京パラリンピックの出場を禁止され、その後も国際大会から締め出されています。この現状に対し有森さんは、「そもそもオリンピックは選手個人、もしくは団体による競技大会であり、国と国との対抗戦ではない」と述べた上で「国として選手をひとくくりにして排除しても平和的解決にはつながらない。五輪憲章を掲げているのだから、もう少し丁寧に判断してほしかった。このままでは排除された選手たちが国際大会の場に復帰する道のりは険しい」と、ロシアやベラルーシの選手の立場に寄り添いました。
そこで藤山氏は、「オリンピック競技大会は、個人種目もしくは団体種目での競技者間の競争であり、国家間の競争ではない」という五輪憲章の一文をあらためて掲示。有森さんは、「選手の中には国旗を掲げてメダルを取ることを目標に戦っている人もいる。それでも五輪憲章の根本原則を軸にしないと、本来の五輪のあるべき姿が崩れていく恐れがある」と警鐘を鳴らします。「五輪は国と国との対抗戦ではないし、世界選手権のようなチャンピオンシップでもない。標準記録はあるものの、それに満たなくても各国から1人は参加していいというルールがある。あくまでも『平和の祭典』であり、メダルの数を数えたり、国別の順位を決めたりすることには矛盾があることに疑問を持ってほしい」と学生たちに投げ掛けました。
さらに有森さんは、「メダルを逃して謝罪する日本人選手の姿をよく見るが、メダルが取れなかったことで自分を卑下する必要はない。自分をたたえることが支えてくれた人たちへの感謝になるはず」と続け、五輪は個人もしくは団体が競い合う中で、自身を高め、互いを認めることこそ重要だと強調。「競技前の記者会見で『本調子ではないけれど頑張ります』とコメントする選手がいるが、これは応援している人に対しても、一緒に戦う選手たちに対しても失礼」とスポーツマンシップの在り方についても疑問を呈しました。
そんな有森さんにとって、東京五輪からの新種目、スケードボードの選手たちの姿は印象深いものだったといいます。「スケードボードの選手たちは、互いの健闘をたたえ合っていた。メダルが取れた、取れなかったに関わらず、仲間の勇気を称賛し合うその姿は、順位や国を過剰に意識し競い合うほかの競技の選手たちの異様さを浮き彫りにした」。


男女平等な五輪とは
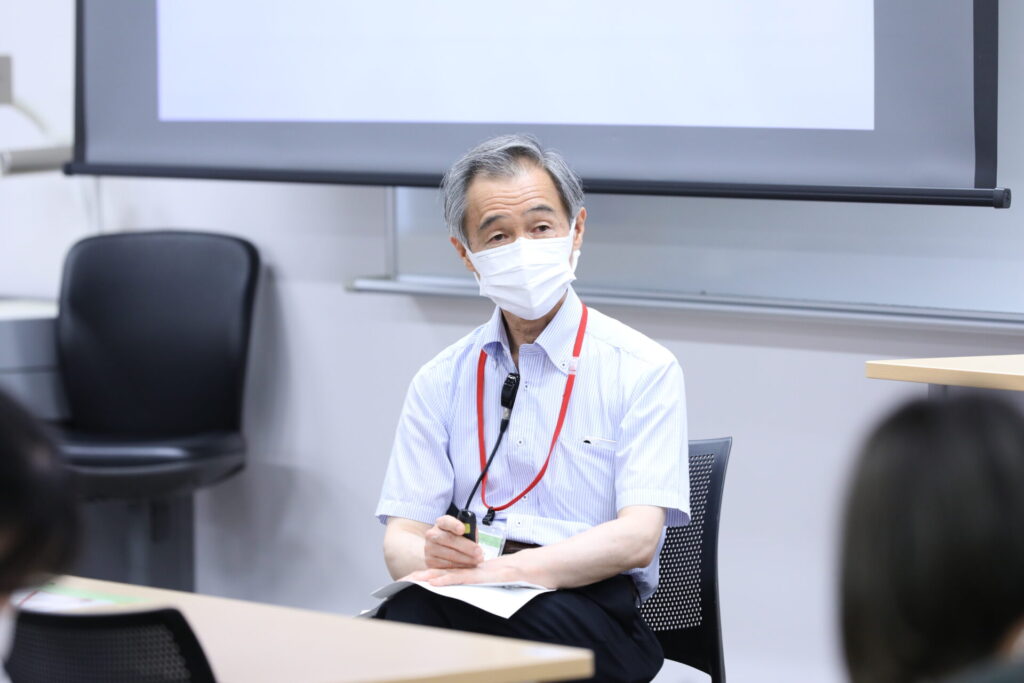
藤山氏は、2024年に開催されるパリ五輪では、長い歴史で初めて男子と女子の参加選手数が同じになる点を取り上げ、何を持って男女平等の五輪とするのか、その問題の複雑さについても有森さんに見解を求めました。「女子マラソンは1984年のロサンゼルス五輪で初めて採用された種目。当時は女性の体力的な問題が懸念されていたが、昨今では女子マラソンへの見方は変わってきた」と有森さん。陸上競技においては男女平等を声高にうたう場面に遭遇しなかったものの、「男性、女性という性別だけではくくれない世の中になってきていると感じる」と話します。「たとえば、生まれながらにして男性ホルモン値の高い女子選手の女子種目への出場を制限するような規定もある。ホルモン値をコントロールし、本来の自分の体を変えないと出場できないというのは、その人の基本的な人権を脅かすことにもなりかねない」とし、「一般社会のジェンダー問題がスポーツ界の問題にもなってきている。これを契機に、皆さんも男女平等について考えてみてほしい」と呼び掛けました。
順風満帆ではなかった有森さんの競技人生
対談の終盤は、有森さんの競技人生について話が及びました。中学、高校と、大きな大会で成績を残したことがなく、大学4年生の時は体育の教員になるつもりだったという有森さん。教育実習先の学校で「体育の先生って頭良くないんでしょ?」と生徒から思いも寄らぬ言葉を投げられ、スポーツ選手としてこのイメージを覆すことに興味を持ち、競技生活を続けることにしたといいます。「大学4年生の夏に、実業団に挑戦したいと両親を説得。予備知識を持たないまま、リクルート陸上部の門を叩いた。そこで初めてマラソンの名指導者、小出義雄監督にお会いし、1時間かけて陸上に懸ける思いを熱弁。『君の根拠のないやる気に興味がある』と監督に言わしめるに至り、入社させてもらえることになった」とのこと。当時は練習メニューをこなすだけで精いっぱいだった有森さんに対し、小出監督は決して「早く走れ」とは言わず、「何時間かかってもいいから、メニューはこなそう」と説いていたそうです。その言葉に従いながら、1日に30~40km、月に1,000kmと走り続けているうちに、有森さんはめきめきと実力をつけていくことになります。
そして、そんな血のにじむような努力の結果、ようやく手に入れたバルセロナ五輪の切符。しかし、有森さんは手放しで喜べなかったといいます。「女子マラソンの代表枠は3人。すでに2人は内定していて、残る1枠を松野明美選手と争うかたちに。当時は明確なオリンピックの代表選考基準がなかったこともあり、最終的に代表に決まった私を批判する人も少なくなかった」。そんなプレッシャーの中、有森さんはバルセロナ五輪で見事銀メダルを獲得して凱旋帰国します。「飛行機を降りて通路に出て無数のカメラのフラッシュを浴びた瞬間、メダルが取れて本当に良かったと思った。この時、メダルがまるで防弾チョッキのように感じられた」。
その後のアトランタ五輪までの4年の間も大変な道のりだったという有森さん。足底筋膜炎の手術を乗り越え、再びオリンピックの舞台に立ちます。「よくぞここに戻ってこられたと思った。そして、続く自分の人生の武器として、どうしてもメダルが欲しかった。誰かに自分の言葉を聞いてもらうためにはメダルが必要だった」。そして、見事銅メダル獲得を果たした有森さんは、目標にたどり着くまでの過程で悔いなくやり切った自分をたたえ「自分で自分をほめたい」、そう口にしたのでした。


未来のオリンピックは皆さんの手で

2つ目のメダルを手にした有森さんは、その後自らプロを宣言。今では当たり前となった選手の肖像権の自己管理やCM出演など、後進に新たな道を開きました。そんな有森さんは、五輪の未来について「スポーツを通した平和の祭典という基本を崩してほしくない。世界にまたがる祭典なので、さまざまなメッセージや社会の気付きを表現し、人間社会に寄与できる場であってほしい。世界中のすべての人たちをつなげる架け橋となり、大きな平和の象徴となる祭典であってほしい」と展望を語りました。「未来の五輪を変えていけるのは、大会運営当事者ではなく皆さんの声だけ。人ごとと考えずに自分の声でオリンピックを変えていく楽しみも見いだしてほしい」と呼び掛け、「五輪は選手のためだけのものではない。選手ファーストは競技当日だけで、基本は社会ファースト。さまざまな人々が共存する中で育んでいくのが五輪。ぜひ皆さんの手で未来の五輪を育ててほしい」と結びました。
グループワークでオリンピックの将来像を考える
有森さんと藤山氏の対談の後、学生たちは「実践女子大生が考える五輪の将来像」というテーマで行うプレゼンテーションに向け、グループに分かれてブレストを行いました。開催規模、開催時期、開催地はどこがいいか、参加国、参加者(男女)はどうするか等々、作戦を立てるにあたり、有森さんに直接質問しに行く学生の姿も見られました。
今回の特別講義から拾い上げたヒントを盛り込みながら、学生たちはどのようなオリンピックの将来像を考えるのか。プレゼンテーションは、今後の「国際理解とキャリア形成」の授業の中で行われる予定です。

深澤教授の話

スポーツニッポン新聞社様とのコラボ講座は、今年で5回目を数えました。
「東京2020」について、共に考え、共に参加することを楽しみに進めてまいりましたが、延期、そして無観客開催と、想定外の変化の中で行われた大会から1年、大切なのはしっかりと振り返ること、まさにレガシーを考えることに意義があると考え、本年も継続して実施いたしました。
そして、今年も有森裕子さんと藤山健二記者にお越しいただきました。
オリンピアンの立場から、また現場での長い取材経験からの視点は、とても興味深い内容でありました。とりわけ、オリンピックパラリンピックは、国別対抗ではなく、個人と個人が競い合い高めあうことであるというお話しは、今後のオリンピックパラリンピックを考える上で大変貴重なお話しでした。この場を借りて厚く御礼申し上げます。
2022年7月27日 スポーツニッポン新聞に掲載

今回の取り組みが7月27日(水)のスポーツニッポン新聞にて掲載されました。また、オリンピック・パラリンピック1周年記念セレモニーにも本学が参加しており、その取り組みも記載されています。