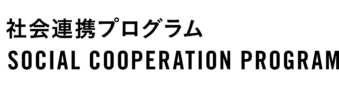東京2020オリンピック競技大会開幕を18日後に控えた7月6日(火)、五輪女子マラソンメダリストの有森裕子さんが、本学渋谷キャンパスを訪れ、特別講義を行いました。
有森さんは、新型コロナウイルスの感染者急拡大で大会開催に批判が高まるなか、「オリンピアンとしては、オリンピックそのものが悪いとは全然思っていない。社会との関わりの中で存在するオリンピックの存在意義を考えてみて欲しい」と強調。また、コロナ禍で不安な大学生活を強いられる学生たちに「自分の思いと自分のプラスを消さないこと。それさえあれば、できないことはない」と呼び掛けました。
授業は、2~3年生が対象のキャリア教育科目「国際理解とキャリア形成」の中で行われ、スポーツニッポン新聞社の藤山健二編集委員と有森裕子さんの対談が実現しました。指導教授は文学部国文学科の深澤晶久教授(キャリア教育)です。今年度は学生26人が履修。コロナ禍でオンライン講義を余儀なくされた昨年と違い、今年度は教室で行われました。
未熟な?オリンピック
対談は冒頭、コロナ禍で異例ずくめの東京オリンピックに関する話題でスタートしました。感染者が急拡大するなか、開催それ自体にも批判がある今回の大会をどう評価するか。有森さんは「藤山さん、こんなに想像つかないオリンピックは今までありましたか?」と藤山氏に水を向け、同氏も「これまでのオリンピックの中で、初めてです」などと、応じました。
その上で、有森さんは学生たちにも問い掛けます。「(今回のオリンピックの)イメージが悪いのは、どこが悪いのかを皆さんに聞きたい。オリンピックそのものが本当に悪いのか。今起こっているコロナ禍の現実がおかしいのか」。有森さんは「私は、オリンピックそのものが悪いとは全然思っていない」と強調した上で、「そこは本当に一番間違えてほしくない」と訴えました。
ただ、組織委員会などを含む大会主催サイドが、これまで通りのスタンスのままでいいのかというと、そうとも言い切れないようです。というのも、今回のオリンピック開催に従来のような一般の圧倒的支持がないのも事実だからです。
この結果、有森さんは「非常に毎日、悩ましい日々を過ごしている」と胸中を明かしました。けだし、「社会との関わりの中で存在するオリンピック開催であれば、すべてに優先されるというのは、自分たちの勘違いではないか」と自問自答していると言い、「(そういうことを)今まで考えてこなかったところに、やはり『オリンピックが未熟だった』と凄く感じている」「本当の意味で、社会の中で論ずべき自分たちの存在意義を考えてこなかったことが、今露呈している」などと強調しました。

オリンピアンはエリートばかりか?

他方、藤山氏も有森さんとは別の角度から、東京オリンピックの課題を探ります。藤山氏は自らの取材体験を通して、「オリンピックに無関心、反対と言う人たちは若い人が多い」と語り、若者たちの声に耳を傾けたのです。
「どうして無関心なのか、若い人にいろいろ聞いてみると、『オリンピックに出場するような選手たちは、小さい頃からエリートで、特別に育てられてきたような人とばっかり。自分たちと全く住む世界が違う人なので、オリンピックは勝手にやってくださいよ』みたいな人が、とても多かったんです」と藤山氏。
オリンピックに出場するアスリートは、本当に絵に描いたようなエリート選手ばかりなのでしょうか。藤山氏は対談を通じて検証を試みます。そのアンチテーゼともいえるのが有森さんの競技人生といえるからです。対談では有森さん曰く、「エリート街道とは無縁の、変な街道」の競技人生を振り返りました。
無名の存在から、一躍五輪の銀メダリストに
翻って、有森さんが陸上競技の表舞台に登場したのは、1990年の大阪国際女子マラソンからです。初マラソンで2時間32分51秒の初マラソン日本最高記録をたたき出し、6位に入賞。2年連続で出場した翌年の大阪国際女子マラソンも、2時間28分1秒の日本最高記録で2位に入り、トップランナーの座を不動のものとしました。翌1991年夏、東京開催の世界陸上は4位。そして1992年夏のバルセロナ五輪女子マラソンで銀メダル獲得と、一気に世界の最高峰へ駆け上がるのです。
この間、わずかに2年半。ところが、それ以前は本当に無名で、後の五輪銀メダリストが陸上競技界で注目を浴びたことは、ほとんどありませんでした。故障がちで、そもそも満足に走れなかったせいもあります。それ以前の有森さんは、どこで、何をしていたのでしょうか?
競技人生の始まりは「門前払い」から
有森さんが陸上競技を始めたのは、岡山市の私立就実高校に入学してからでした。市内の公立中学校時代はバスケットボール部。ただ、有森さんは持久力に優れ、その特性を活かして校内運動会の800m走で3年連続優勝したと言います。それがきっかけで、バスケットボールから陸上に目を向け、「バスケの下手な自分より、走ってゴールテープを切れる自分の方がいい」と考え、陸上競技転向を決意したと振り返りました。
しかし、高校生となった有森さんは、陸上部に入部を希望するも、同部の顧問から「素人はいらない」とあっさり門前払いされてしまいます。就実学園は中学・高校・大学の一貫校で、同高校の運動部は全国優勝したバレー部に代表されるようなスポーツ強豪校。中等部から内部進学した逸材がゴロゴロしていました。他校から入学した素人同然の有森さんは相手にしてもらえなかったのです。ただ、そこは後にマラソンで驚異の「粘り」を発揮する有森さんです。1か月かけて陸上部顧問の先生のもとに通い詰め、とうとう根負けした陸上部顧問から仮入部を勝ち取りました。
そうまでして陸上をやりたい気持ちが強かった理由は何だったのでしょうか。有森さんは「頑張ったら人から評価され、自分の自信にもなったものが、運動会で走ったことが初めてだったんです。陸上がしたいというより、唯一走ることで得られた自信を手放せなかったんです」と話してくれました。

トライアスロン転向を目論むも、あっさり頓挫

ただ、有森さんによると、高校時代は全くの鳴かず飛ばず。実績はゼロでした。国民体育大会やインターハイとはまるで無縁で、陸上部顧問の恩師の推薦で日本体育大学を受験した際は、面接官から「有森さんはどうしてこの大学に入れたんですかね?」と不思議がられる始末でした。大学入学後も、1年時に関東学生選手権大会で3000m2位に入賞し周囲を驚かせたことはあっても、またもや足を故障。やがて名門・日体大陸上部の中で、その存在を忘れられていきます。
この間、有森さんは密かにトライアスロンへの転向を目論見ます。当時、トライアスロンにはまだ女子の第一人者がいなかったからと言いますが、要は「現実逃避」です。親からの仕送り10万円の大枚を全てはたいて、高額なトライアスロン用自転車を購入。転向計画の準備は着々と進展するかに見えたのですが、早晩、計画はあっさり頓挫してしまいました。「肝心の自転車が盗まれてしまい、いきなり目の前から消えてしまいました」。有森さんは、はっと我に返ります。その時の心境を、高額な自転車を盗まれた悔しさよりも、「自分は何をしているのか。何のために大学に進学したのか。走るためだろう」と振り返りました。
未来切り拓いた、小出監督との出会い
卒業後は体育の教師になるつもりでした。高校と大学を通じて実績ゼロの自分に、実業団から声が掛かることは有り得なかったからです。そう頭では分かっていても、これまでの陸上競技人生に「不完全燃焼感」は拭えませんでした。そんな時に岡山市内の自宅に掛かってきたのが、リクルートの小出義雄監督からの一本の電話でした。後に有森さんが「小出監督の勘違いだった」と分かった監督からの電話が、有森さんの未来を切り拓きます。
小出義雄監督は、女子選手育成に卓越した手腕を発揮する名伯楽として当時から知られていました。2019年4月に80歳で亡くなりますが、有森さんのほか、2000年シドニー五輪金メダリストの高橋尚子さん、1997年世界陸上アテネ大会女子マラソン優勝の鈴木博美さん、2003年世界陸上パリ大会女子マラソン3位の千葉真子さんなどを育て、幾多のトップランナーを世に送り出しました。
有森さんは、友人の紹介を頼りに手紙を通じて実業団のリクルートにアプローチ。小出監督は同社陸上部のマネージャーから入部希望の有森さんの存在を知らされたようです。電話での2人の会話は、小出監督が過去に有森さんと面会したことがないのに会ったものと勘違いしていたせいで、どうにもチグハグなものでした。結局、「多分、僕ね。物忘れがひどいから、思い出すかもしれないから、会ってみよう」ということになり、有森さんは翌日、千葉のリクルート合宿所の小出監督のもとに嬉々として向かいます。

熱意を監督に認めてもらう

有森さんによると、1時間ほどの面談は「逃げ出したくなるような面談」だったそうです。小出監督は「有森さん、国体は何位?」「インターハイは?」などと質問を重ねますが、いかんせん、有森さんは高校や大学で実績ゼロ。ひたすら「入部したい」「これから実業団で頑張りたい」と熱意を強調して直訴するしかありませんでした。小出監督もようやく事情を呑み込めたようで、最後の方は困り果てていたと有森さんは述懐します。
有森さんは「(僕の)勘違いだった。あまり情報がなかったから呼んでしまったが、ちょっと無理だよ」と小出監督が言ってくれれば、入部は諦めていたと言います。しかし、小出監督から返ってきた答えは意外なものでした。
「有森さん、今うちね、いい選手が5人いる。高校チャンピオンや日本記録保持者、インターハイ・国体チャンピオン…。そうそうたるメンバー。素質や実績、肩書き…すべてパーフェクト。ただね、有森さん。人間は、どんなに素晴らしい素質や肩書き、実績を過去に山ほど持っていても、『これからどうしたい』『夢や目標を持っているか』ということが、本当に大事なんだ。それをね、有森さんは見事に持っている。僕もびっくり。これほど持っている人を目の前で初めて見た。もっとびっくりなのは、これだけ何も実績を持ってない人が、よくぞここにやってきたということ。その根拠のないやる気、とっても興味がある。僕はあなたの根拠のないやる気を形にしてみたい」。
千葉での面談から2日後、岡山市の実家に帰っていた有森さんにリクルート社人事部から電話で採用の連絡が届きました。1989年、有森さんは日体大を卒業と同時に、晴れてリクルート社に入社しました。
悔しさバネに、マラソン転向
入部後の有森さんは、1年目の秋にマラソンに転向します。当初は国体種目の1万メートルを目標に練習していましたが、岡山県の最終予選で優勝するも、陸上部が選手登録をしていなかったミスで失格。岡山県代表の夢は儚く消えました。しかし、陸上部から謝ってもらえるどころか、小出監督からは「お前に実績がないから、そういうことになるんだ」と突き放される始末。悔しさの余り、涙ながらに寮の自室の壁を足で蹴りながら、「今に結果を出してやる。今に見てろ。絶対忘れられない選手になってやる」と誓ったうえでのマラソン転向でした。
一日40キロの猛練習で才能開花
転向後のマラソン練習は、1か月間で1200キロ、一日平均で40キロに達するハードなものでした。成人女性の一日平均摂取カロリーは1400~2000カロリーと言われますが、有森さんは「4000カロリーは普通に摂っていた。そうでないと痩せてしまう」と述懐します。
また、バネがなくてスピードが出ない有森さんに、小出監督がタイムを要求することはなかったと言います。代わって小出監督が要求したのは、他人の倍以上のメニューの消化でした。小出監督から「お前な。42.195kmを全力で走らなきゃいけないから、その距離(40キロ)が普通にならなきゃいけない」と言い含められ、有森さんは「はあ?そうなんですね」と、さしたる疑問も抱かずに、毎日の猛練習に耐えていたそうです。

コンタクト片方で駆けたバルセロナ五輪

こうして転向後2年で迎えたスペインのバルセロナ五輪。結果は周知の通り、有森さんは銀メダルに輝きました。日本女子選手で64年ぶりのメダルです。対談では、当日の朝にホテルでコンタクトレンズの片方を失くし、片目だけでレースを走ったこと。また、沿道のスペイン語による「アニーモ」という声援を、自分のニックネームである「アリモ」と聞き違え、大いに気をよくしてコースを駆けたことが、エピソードとして紹介されました。有森さんは、藤山氏の「銀メダルを実感した時はいつ?」という質問に対し、「表彰式後にホテルに戻り、メダルを掛けたまま鏡に映る自分の姿を見た時」と語りました。
足の故障など、心身ともにどん底を経験
しかし、バルセロナ後は栄光の競技人生が暗転。周囲との軋轢から心身のバランスを崩し、足のケガも重なって、スランプで走れなくなってしまいました。
有森さんによると、バルセロナ直後は「優勝したエゴロワ選手の安定した走りに刺激をもらい、『私もあんなフォームを身に付けるんだ』『もっと筋力をつけるんだ』と、本人はモチベーションを失っていなかった」と言います。
ところが、周囲の反応は全く違ったものでした。「これで引退できるね」「これからは指導者だね」などと、メダル獲得を花道に競技人生の引退を勧めるかのような接し方だったと言います。それが有森さんには疑問であり、不満でした。「自分はメダル獲得を契機にさらなる高みを目指すつもりなのになぜ?」。そうした周囲の接し方が我慢ならない有森さんでしたが、反発すると逆に誹謗中傷を受ける始末。タイミングが悪いことに、バルセロナ後は疲れから体はガタガタ、足の痛みも悪化し、記録は落ちる一方でした。もちろん、そんな「過去の人」の言葉に重みはありません。「これでは誰も私の話など聞いてくれない」と焦って走ると、さらに記録は落ち、ますます袋小路に陥ってしまいました。
転機は足底筋膜炎の手術でした。手術は成功。再び走る意欲を取り戻し、翌1995年夏にアトランタ五輪の選考レースを兼ねた北海道マラソンに出場。大方の予想を覆して優勝し、アトランタ五輪への切符を手にしました。
ただ、アトランタ五輪出場に賭ける気持ちは、無心で臨んだバルセロナ五輪とはまるで違いました。心身ともにどん底を経験した有森さんのみが知る固い決意を秘めていたのです。「何色でもいいから、何が何でもメダルを獲らなければならない」。それは「オリンピックは手段。決してゴールではない」という、自らの信念の正しさを証明するため必要なメダル獲得でした。自分の言葉に耳を傾けてもらうには「過去の実績ではなく、今の明確な実績が必要だった」と信じて疑わなかったのです。
「自分をほめたい」は、納得感から出た言葉
そして迎えた1996年7月のアトランタ五輪。有森さんは再び女子マラソンのスタートラインに帰ってきました。4年間の紆余曲折を経て、たどり着いたスタートラインは「すごく気持ちのいい、変な緊張など何もない」という非常に落ち着いていたものだったそうです。結果は銅メダル。ゴール直後に、この年の流行語大賞にもなったあの言葉が生まれます。「自分で自分をほめたい」-。
それは「単に銅メダル獲得という結果に対して出た言葉ではない」と有森さんは強調します。「オリンピックは、あくまで手段であり、ゴールではない」という、自らの信念を証明するため、どうしても必要な2度目のメダル獲得でした。対談では、あの感動の言葉がゴール直後に口をついて出たゴール直後の心境を「全てにおいて自分しか知り得ない内容を、求めるもの全てをクリア出来たという納得感から出た言葉だった」と明かしてくれました。

「どんな状況でも、自分の思い大事に」
対談の最後に有森さんは、学生の質問に応じます。その際、有森さんが語ったのは、「マラソンを走った経験がある?」と学生に尋ねた上で「(マラソンは)誰でも出来る。絶対に42.195キロを走れる。なぜなら、歩こうが止まろうが、前にさえ進めば、いつか42キロ先のゴールに絶対にたどり着けるからだ」というシンプルな事実でした。そして学生に訴えます。「できない唯一の条件があるとしたら、それはあなたができないと思っているか、思っていないかなのでは?」。
学生たちとの質疑応答ののち、有森さんはコロナ禍で不安な日常を送る学生らにエールを贈ります。「人生も(マラソンと)一緒」と強調。続けて、「自分が自分の思いと、自分のプラスを消さないこと。それさえあれば、できないことはない」「どんな状況であっても常に、自分が自分という姿や思いを、ちゃんとあるかどうかを大事にしてほしい。そうすれば、いつでも、どんな状況でも、誰かがそれに気付いてくれるから、出来ないことはないと私は思っている」などと語りました。



深澤晶久教授の話
藤山編集委員のお心遣いから生まれた有森裕子さんの特別講座、昨年は残念ながらオンラインとなりましたが、今年は教室で直接お話しをお聞き出来ることになりました。学生のアンケートからも、様々な有森さんのお言葉が響いたことを実感しましたが、なかでも「どんなに苦しくても諦めないことの大切さ」「自分の信念、いわば軸をしっかり持ち続けることの大切さ」そして、思うようにいかない場面では「せっかく」という言葉を頭につけることでどんなネガティブなこともポジティブなことに置き換わる「魔法のフレーズ」が特に印象的でした。貴重なお話しをありがとうございました。