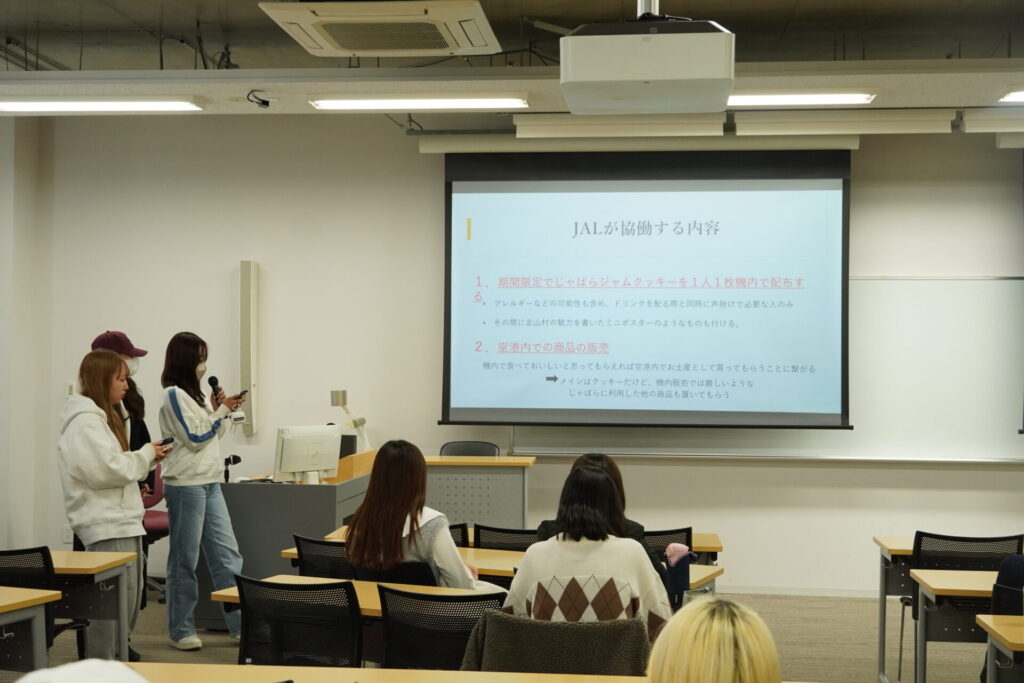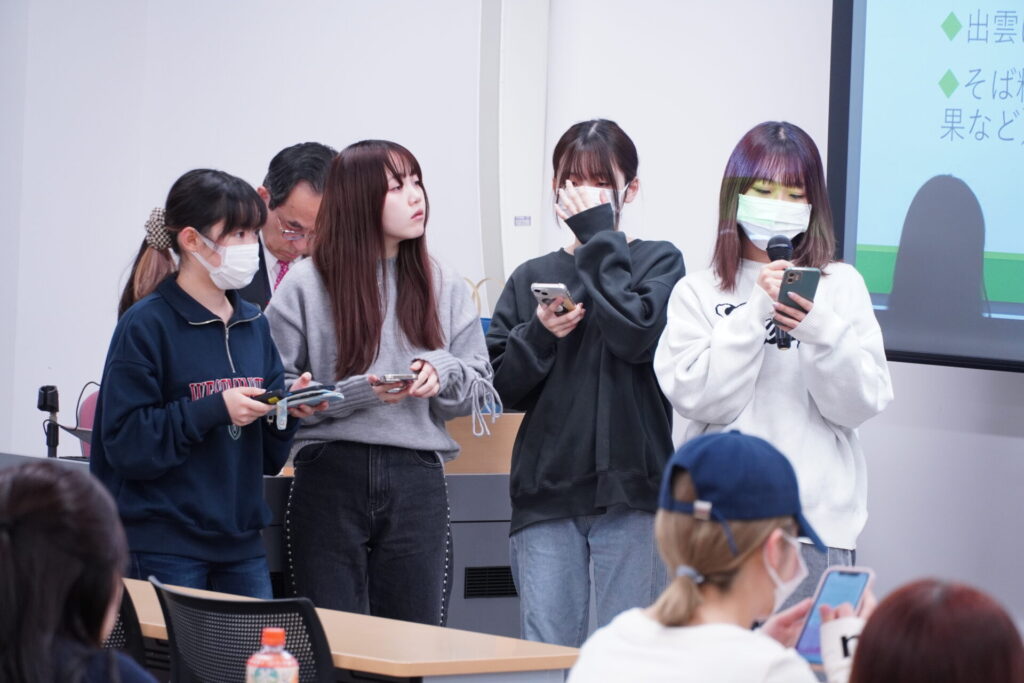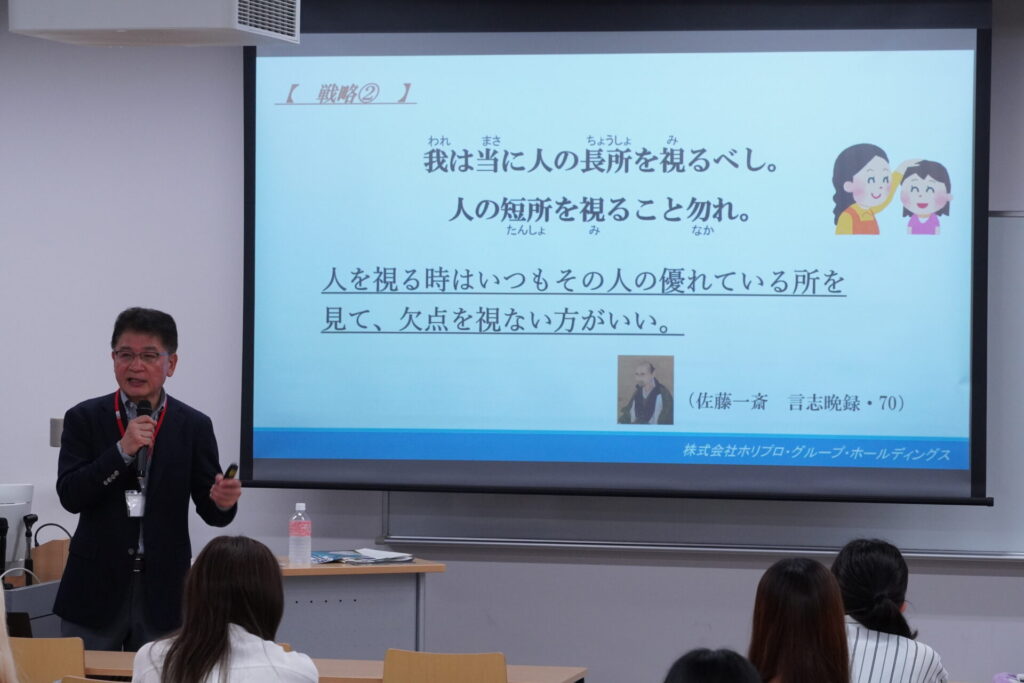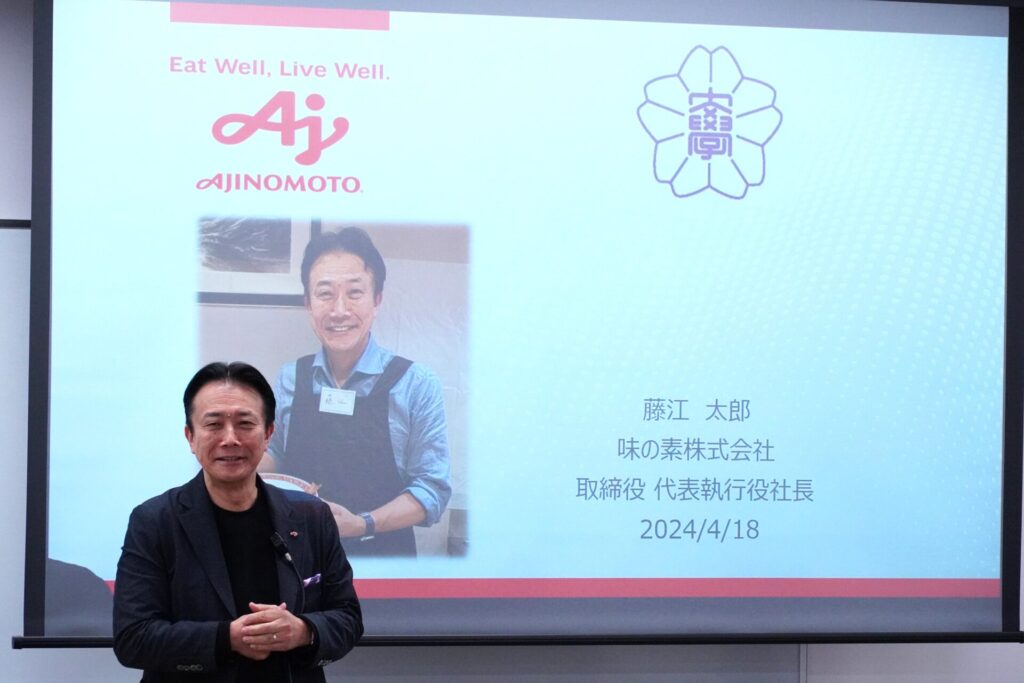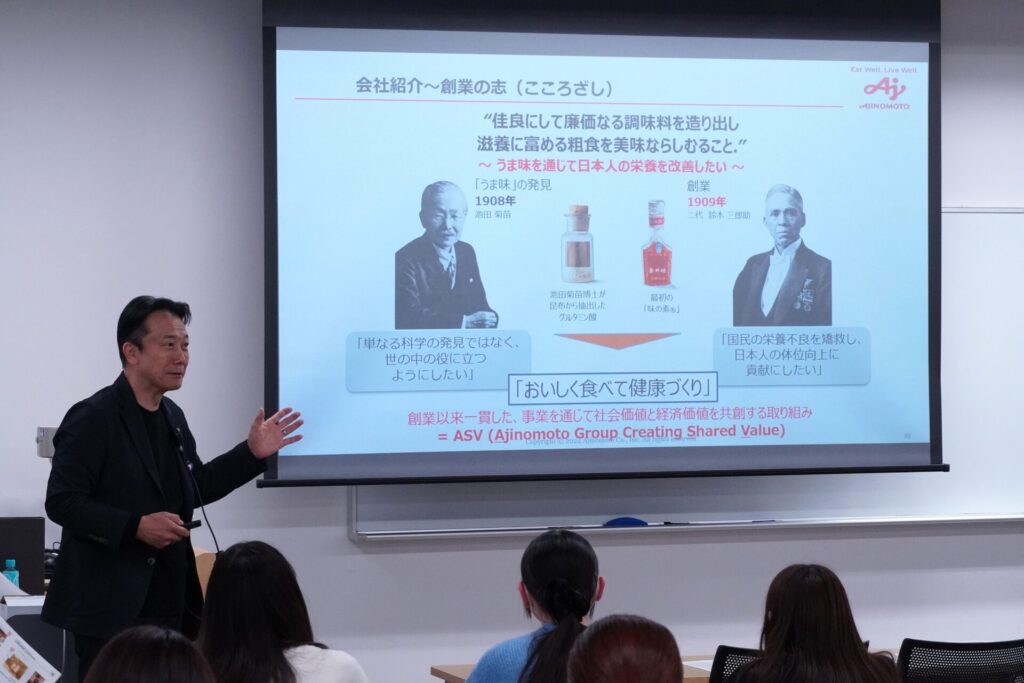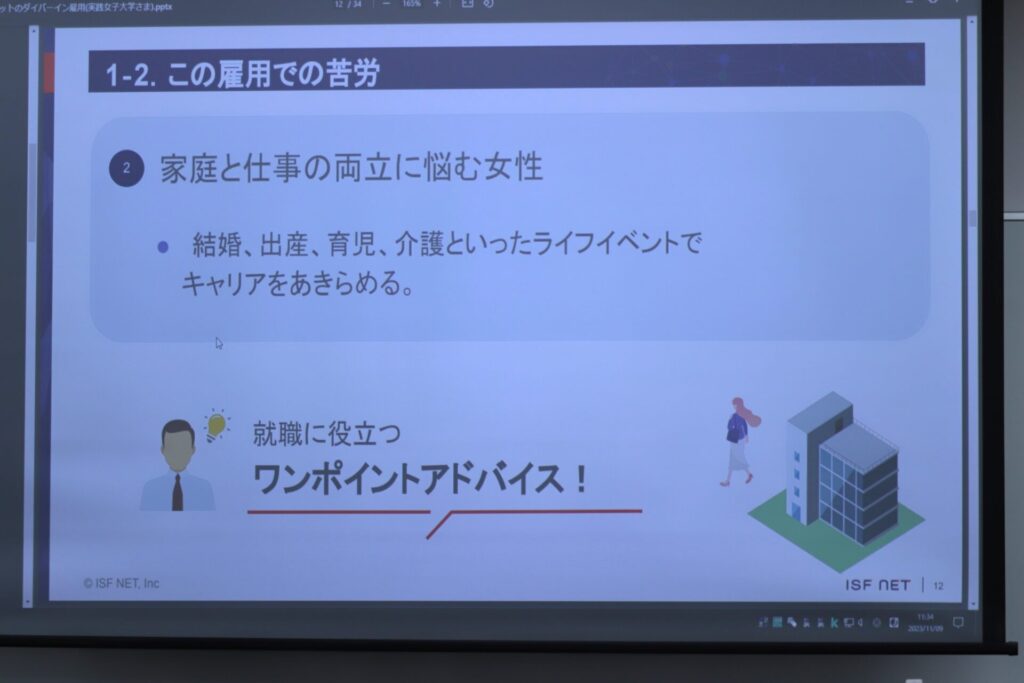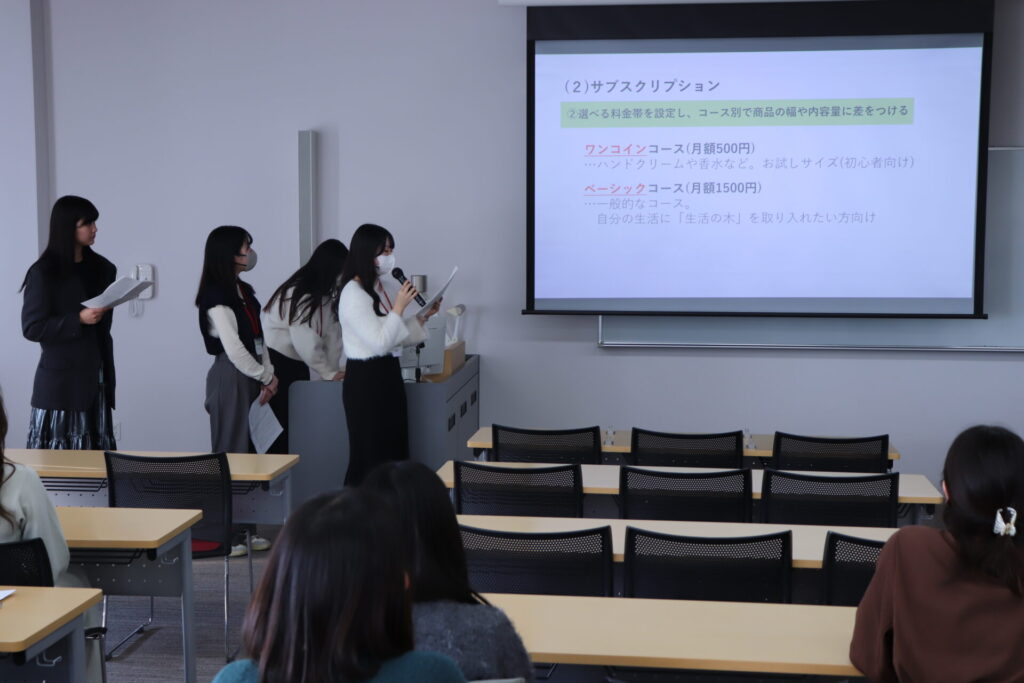スポーツを通じたウェルビーイングとは?パリパラリンピックに出場した舟山選手との交流会を今年も開催しました!
2024年度のJWP(実践ウェルビーイング・プロジェクト)活動として、12月21日(土)に、2024年パリパラリンピックで5位入賞を果たした舟山真弘選手をゲストにお迎えし、パラリンピックの舞台裏のお話を聞きながらウェルビーイングなひとときを過ごしました。
昨年度に続き、今回も「スポーツを通じたウェルビーイング」をテーマに、対談形式で舟山選手からお話を伺いました。

ゲスト:舟山 真弘(ふなやま まひろ)選手
現在、大学2年生。 4歳で小児がんの一種である「右上腕骨 骨肉腫」に罹患。1年2か月間入院し、手術と抗がん剤治療を受けました。手術では、利き手であった右腕の肩関節と上腕骨を切除し、足の細い骨を移植しました。右腕は上がらなくなり、細い骨の骨折に細心の注意が必要となりました。
昨年度ゲストとしてお迎えした際は、パリパラリンピック出場を目標に掲げていた舟山選手。実際に夢の舞台への出場を果たし、その舞台裏や今後の目標について話を伺いました。
まずは舟山選手のご紹介も兼ねて、パラリンピックの映像を本人の解説付きで上映しました。パリでフランス現地の選手との激しい攻防戦の様子を見て、参加学生からは「おぉ~」と歓声が上がっていました。また、質問コーナーを設け、卓球についてだけでなく、気になる私生活についてもイベント参加者の方々から沢山質問していただき、丁寧に答えてくださいました。
◆当日の質問より(一部抜粋)
Q.試合前はどのように過ごしますか?
A.なるべく卓球のことを考えないように、いつもどおり過ごすようにしています。散歩をしたり、漫画を読んだりします。また、試合の直前まで音楽を聴きます。最近は、アニメ「アオアシ」の主題歌であるSuperflyの「Presence」を聴いています。
Q.舟山選手の勝負メシはありますか?
A.勝負メシという感じではないかもしれませんが、試合前は、いつもセブンイレブンのマーガリン入りバターロールを食べるのがルーティーンになっています。

イベント中盤では、卓球体験と舟山選手の神業チャレンジ企画を行いました。
今回、高大連携の一環として本学の中高卓球部から5名の生徒が参加し、舟山選手との卓球対決が実現しました。パラリンピック出場選手との打ち合いは白熱し、会場は大盛り上がりでした。また、神業チャレンジでは、卓球台の端に置かれたペットボトルを打ち抜くという難易度の高いチャレンジに挑んだ舟山選手でしたが、あっさりと成功させ、会場は感嘆の声に包まれました。

イベントの後半では、クイズ大会を行いました。
質問コーナーで上がった話を中心に、全部で10問用意されました。舟山選手が考える卓球の魅力や流行りのMBTIなど幅広い質問があり、正解が発表されるたびに参加者は一喜一憂していました。
また、正解数の多かった上位3名には、舟山選手の直筆サイン色紙が送られました。
最後に、舟山選手にとってのウェルビーイングについて話を伺いました。
舟山選手は、「自分がやりたいと思うことをこれまで続けてきた。今回パラリンピックに出場し会場の歓声を聞いたときに、自分のやりたいことが誰かに元気を与えられている、誰かのためになっていると初めて気がついた。卓球を続けてきて初めての経験だった」と語っていました。「自分がやりたいと思うことを継続する」―参加者にとっても心強い言葉と経験談を聞くことができたのではないでしょうか。
同世代でありながらも世界を舞台に活躍する舟山選手との交流会は、終始笑顔が絶えない、まさに「ウェルビーイング」なイベントとなりました。
運営学生からのコメント
・まずは昨年に引き続き、今年も舟山選手にお越しいただくことができ、とても嬉しかったです。初めてのパラリンピックで5位入賞という素晴らしい成績を残されたことを、同世代として本当に尊敬しています。パラリンピックが終わり、「お疲れさま会」と副題をつけて和やかな雰囲気で開催できてよかったです。運営としては、私たちならではの空気感で楽しい企画を立案できたと思います。また、4年間で最後の企画運営で、司会を担当できたことが本当に嬉しかったです。トラブルがありながらも、事後アンケートではたくさんの方に好評をいただき、やりがいを感じました。来年以降も後輩たちが引き継いでくれることを楽しみにしています。
・昨年からの繋がりがある企画であったため、参加者に『1年前よりももっと「スポーツとウェルビーイング」について考えることができた』と思ってもらえるように尽力しました。4年生として運営メンバーをまとめる役割でしたが、ひとりひとりが得意な分野で活躍できたのが良かったです。当日は、裏方の仕事でしたが、参加してくれた実践女子学園中高の皆さんと活発にコミュニケーションを取ることができました。また、舟山選手の意外な一面や、全員が楽しく卓球をする表情が見られ、大成功に終われたと思います。大学生最後の活動ということもあり、全てが感慨深いもので、一個人としてもこの企画に参加できてとても楽しかったです。
・昨年に引き続き同じメンバーで企画ができたため、昨年の反省を生かし、さらに良い企画を立案できたと感じます。また、今年度は、実践女子学園の中高生をお招きし、舟山選手との卓球体験を行いました。中高生の皆さんからは、「すごく刺激を受けた」と感想をいただけたので良かったです。参加者の皆さんが、舟山選手の話と卓球体験により体を動かすことで、スポーツとウェルビーイングとは何か自ら考える良い機会になったと思います。運営をやっていて本当に楽しかったので、一緒に企画してくれた運営メンバーの皆さんにも感謝です。
・昨年と引き続き同じメンバーで運営をし、よりスムーズに行うことができました。パラリンピックの映像を本人の解説付きで見ることができたり、前回とは違う「神業チャレンジ」や卓球体験を行ったりし、今回が初めての参加の人も中高生も刺激を受けることができたのではないかと感じました。スポーツとウェルビーイングを通じて、ウェルビーイングの重要性などについて考えるきっかけになったら嬉しいです。初めてのことばかりで戸惑いも多かったのですが、このメンバーで運営をすることができてとても楽しかったです。
・JWPでは、他では経験することのできない特別な活動をできていると感じます。パラリンピック選手をお招きしてのイベントを開催するにあたり、メンバーで数回の話し合いを重ね、前回の反省を生かし、今回はより良いものをつくることができたと思います。また、JWPでは、面白いイベントが多いので、全てに興味を持ち、自然と主体的に動くことができていると感じます。授業だけでは経験できないイベントの幹部やサポートなど、自ら考え動き、成功に導くことができる活動は、短い大学生活においてとても貴重で価値があるものだと思います。