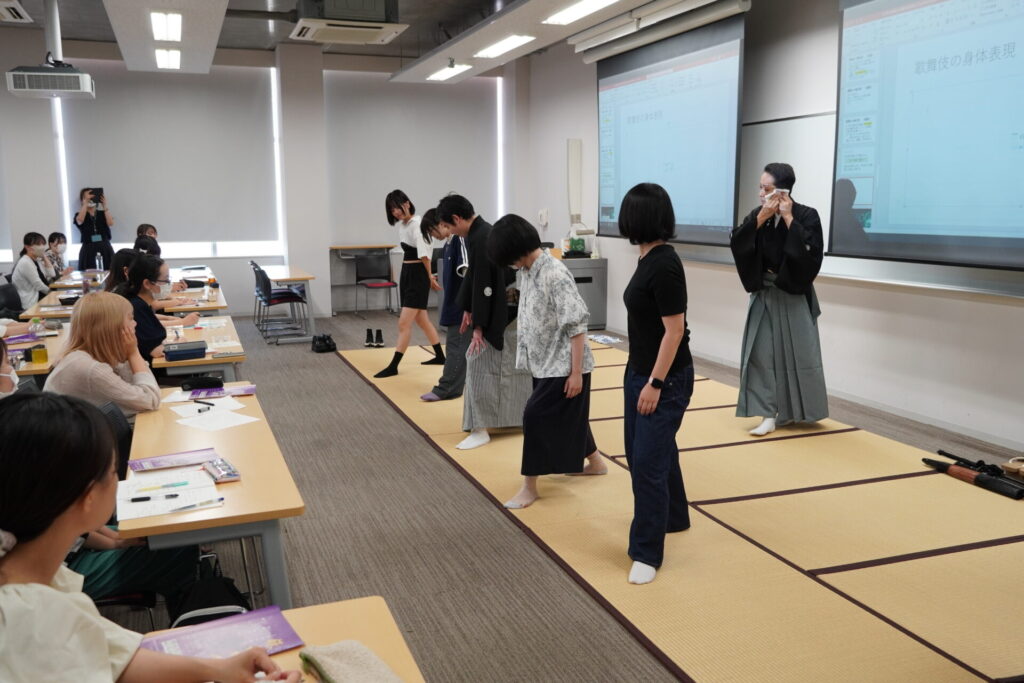京都市と「Jミッション」を実施しました!
本学では、低学年向けキャリア支援を強化すべく、2019年度より企業や自治体との産学連携プログラム「Jミッション」を実施しています。本取り組みは、大学1年生・2年生を対象に「良質な経験・学修の場」を提供することで、学びに対する意欲や自己肯定感の向上を目的としております。学生だけで構成されたチームで、企業や自治体からのミッション(課題)に取り組み、最終的には企業担当者の前で発表を行います。今回は、2019年に本学との連携協定を締結した京都市様のご協力のもと、首都圏で感じられる「京都らしさ」を発掘し、TikTokでPR動画の作成を行いました。
実践女子大学×京都市(2025年2月~3月実施)

初日のキックオフでは、京都市様から京都市の紹介や若者の観光客が少ないといった課題について説明していただきました。また、都内には京都の伝統工芸品や和菓子を扱うお店、京都出身の方がオーナーを務めるお店など京都にゆかりのあるサポーターショップが100件以上あるとの説明がありました。その後、各チームは取材を担当するサポーターショップを決めるドラフト会議を行いました。
2日目は、企業や自治体のブランディング動画やプロモーション動画の制作を手掛ける、シェイクトーキョー株式会社の代表取締役汐田様より、動画作成に関する講義をしていただきました。TikTokの特徴や検索アルゴリズムのお話など、戦略的に視聴数を稼ぐためのコツをプロの視点で解説いただきました。
2日目終了以降、各チームサポートショップへのアポ取り、現地取材、素材撮影を行い、中間発表に向けて動画作成を行いました。
3日目の中間発表では、各チーム作成した動画を京都市様、汐田様に向けてプレゼンしました。汐田様からは、「ここから1週間でクリエイティブジャンプを起こしそうなチームが多く、完成形が楽しみ」というご講評をいただきました。


最終発表では、中間発表でのフィードバックを参考に各チームがブラッシュアップした動画のプレゼンを行いました。生菓子実演が見学できる和菓子店や金継ぎ・茶道が体験できるお店、都内の神社の紹介など、どのチームも京都が存分に感じられる動画に仕上がっていました。映像はもちろん、テキストの入れ方や、音声の入れ方など細部にまでこだわったクオリティの高い動画ばかりでした。
審査は難航しましたが、京都市様から最優秀賞の発表があり、チーム「うめとしゃけ」が見事最優秀賞に輝きました。
このチームは、京都市出身のオーナーが経営する鉄板居酒屋を動画内で紹介し、食事ではなくオーナーの人柄に焦点をあてた動画が高く評価されました。
都内で開催された「高輪桜まつり2025」の京都の伝統工芸ワークショップ会場内で学生が作成した動画が放映されました! また、最優秀チームは京都市公式TikTokアカウントに動画が投稿される予定です。

【参加学生の声】
・ミッションを通して、チームで協力しながら動画作成やパワーポイントの制作、訪問などを行い、チームワークの大切さを実感しました。また、発表に向けて分かりやすく伝える工夫をしたことでプレゼンテーション力が向上し、訪問や準備の過程で予想外の修正点が出た際には、チームで話し合いながら柔軟に対応することで、課題解決力も身についたと感じています。
・このミッションを通じて大きく自己成長することが出来たと感じました。まず、コンセプトを作り上げ、全体的なテーマを具体的なコンテンツに落とし込む力などの企画力から、分析して伝える力など様々な力をつけ成長に繋げられました。
・アポ取りや動画制作という今までやったことがないことに挑戦させていただいて、動画1本を作るのにたくさんの時間と労力をかけていることが改めて理解できました。ひとつのことに対して掘り下げる力というのは全体を通して身についたと思います。